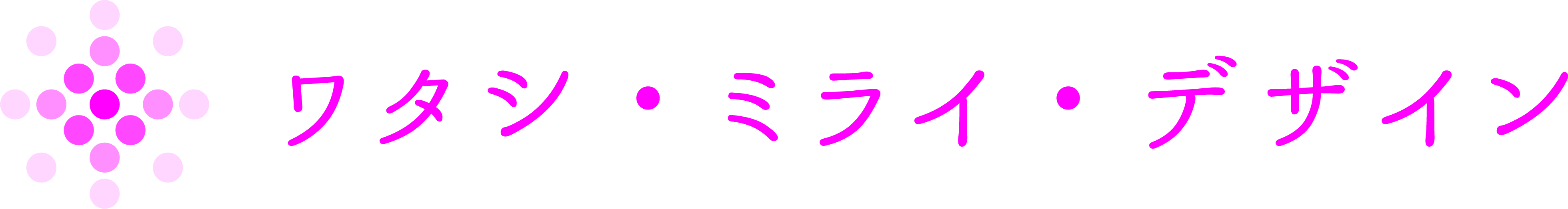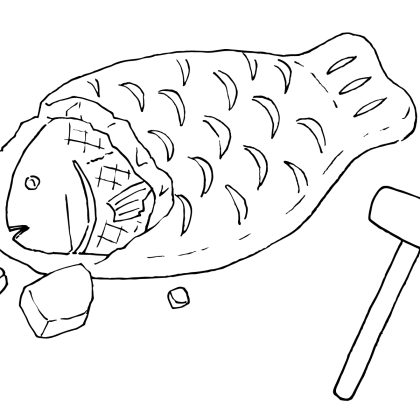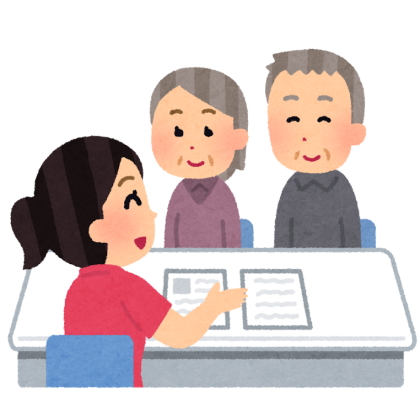2025-02-01
社中の初釜に参加しました
皆さま、こんにちは。この冬は急に寒くなったからなのか、寒さが堪えます。どうぞご自愛ください。
さて、1月のお茶のお稽古は、新年を祝う初釜で始まります。
今回は、薄茶点前の役をいただき、11月からずっとお稽古に励んでおりました。

初釜は、着物着用で、普段お稽古では見ることができないお家元の書付があるすばらしいお道具を使わせていただきます。お値段を想像すると手が震えます。粗相がないようにしなければなりません(汗)。
姉弟子に「落ち着いて、考え過ぎずにお点前すれば大丈夫」と励まされ、何とかお役目果たせました!よかったです!社中の初釜は、身内での発表会のようなものです。緊張はしますが、お茶事を体験できる貴重で、楽しい時間です。
昨年10月の堺まつりで薄茶点前をさせていただいたのですが、その際は風炉でした。しかし、初釜は炉です。背が低い私は、低い位置に釜がある炉の方が扱いやすいです。
-872x1024.jpeg)
ちなみに『炉』は、室町時代中期の茶人、村田珠光が民家にある囲炉裏にヒントを得て茶室に小さな囲炉裏である『炉』を作ったのが始まりだそうです。
炉は、風炉よりも大きく、炭もたくさん入り、大きなお釜を掛けることができ、水蒸気でお部屋全体が温まります。物理的に炉の位置がお客様に近いということもあり、寒い11月~4月が炉の季節です。
お客様への配慮がお道具にも表れていて、奥が深いな~と感心します。
(Yoneda)
関連記事